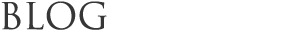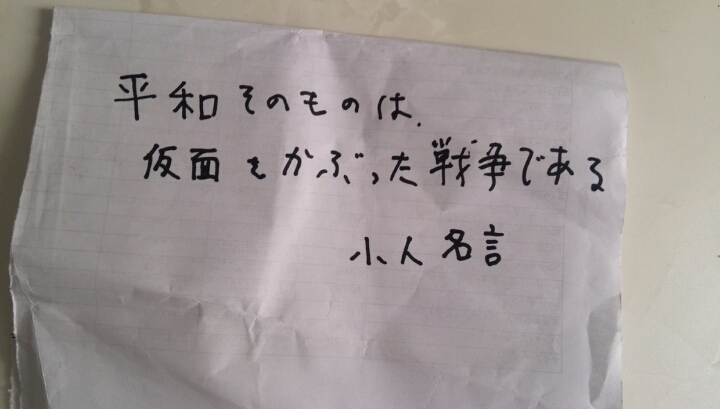- 「なに見てんだよ。捨てるんなら貰ってもいいだろ」と言うおじさんは体長8cmくらいで、あたしの部屋の床にいた。薄暗い中で舌に生えたキノコをカットしてたら現れたのだ。
動揺を隠しつつ「そのキノコどうするんですか?」と聞く。「喰うに決まってるじゃないか。第一、これはお前のものじゃない。俺が栽培してるんだからな。勝手に捨てるなよ」と言う親指サイズのおじさん。「お前、変な手術するから最近味が変わったぞ。まあ、21世紀の味ともいえるか。科学の進歩と相反する精神の貧困さだな。そのキノコは18世紀に大流行した貴重なものなんだぞ。俺がロンドンで憑いてた男にも植え付けてやったら、そいつはコーヒーハウスでごちゃごちゃ面倒くさい理屈をこねるようになりやがったけどな」
なんだかわからないが、おじさんは高い声で早口にまくし立てる。永遠に続きそうな話を要約すると、おじさんは何世紀も生きていて、取り憑いたひとの舌にキノコの胞子を植え付けている、今はあたしだということだ。ジョン・ドライデンとかいう過去のひとも、おじさんのキノコ栽培の犠牲になったらしい。
「口を開けて寝ているお前が悪い」って言われても、花粉症で鼻づまりなんだからしょうがないじゃないか。「それにしてもお前の男の趣味は悪いな。脳みその配置がおかしい奴らばかりじゃないか」とまで言う。あれらは別にお付き合いしてるんじゃなくてバイトなんです、と説明するのはやめて「なんで知ってるんですか?」と聞くと「俺はお前の鞄にいつも潜んでいるぞ。お前の身体は大切な食物の畑だからな。観察し、ときに運命のベクトルを変えている。」
なんとなく感じていた最近の状態は、こんなとこに由来するものなのか。頭の中で言葉が機関銃のように打ちまくられてる感じ。生き急いでるような焦燥感。音と言葉が確かにあると実感する。
「お前の仕事を全うするがよい」と捨て台詞を吐いて、妖精おじさんは何処かへ消えていった。
※これは完全なるフィクションです。
Android携帯からの投稿
CopyRight (C)All rights reserved by ro japan agency