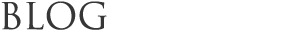-
タデウシュ・コンヴィツキの『夏の終わりの日』。
なんの解説を読まずに観た。ヤバそうな男のひとと悩んでそうな女のひとのふたりしか出てこない。戦闘機か訓練してる飛行機みたいなのが、うるさく飛んでる浜辺での半日。ヤバそうな男のひとは泳げないくせに何度も海に入りたがり、女のひとに助けられたりする。
女のひとは夏休みの最終日らしく、ひとり海を見て泣いたり裸で泳いだりする。
ふたりは浜辺で知り合って、恋愛に発展するようなしないような、でもいい雰囲気になって互いを求めたり突き放したり。雨が降ってきて仲良く雨宿りしたり、奇声をあげて走り回ったり。
鑑賞中、私のなにかが「わけがわかりませ~ん」と叫びそうになったけど、気付いたら最後まで飽きずに集中していた。
あとで解説を見るとヌーヴェルヴァーグの予見的な作品だそうだ。なるほど、わけわからなさはヌーヴェルヴァーグばりだ。砂浜の美しさとか、登場人物の少なさとか、哲学チックに悩んでそうなとことか正にヌーヴェルヴァーグだ。1958年の作品なので当時は革新的だったのだろうと思った。
CopyRight (C)All rights reserved by ro japan agency