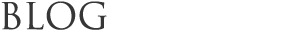「これ、私のワンちゃんのケン!よろしくね」と恵比寿駅の改札出たとこで紹介された。菜摘とは少し前に待ち合わせしていて、アトレをぶらぶらしながら作戦会議をした。
「ど、どうも・・・」と小声で吃るワンちゃんのケンは白くてぶよぶよした巨体のオッサンだった。地方から出張で来るときに菜摘とプレイするそうだ。サイズの合ってないネズミ色の背広にキオスクで買いました?って感じのネクタイをしてる。変な銀の丸眼鏡までしてるのは冗談かと思った。こいつはワンちゃんとかケンとかいうより、村役場って感じだ。
日比谷線口の方面に数件のホテルがあって、そこを目指して歩く。ピンヒールをカツカツ鳴らして歩く身長155cmの菜摘の後を、巨体のオッサンがゆらゆら付いていく様子は、なかなかシュールだ。あたしはふたりを眺めながら歩く。
ホテルで部屋を選んでたら突然従業員が銀色のドアから顔を出し「定員は二名様です」と言われた。するとワンちゃん村役場は「ひ、ひとりは見ているだけなんですぅ!するのは二人ですぅ!」と言う。こいつはアホか。ていうか誰と誰がプレイして誰が見てるってんだよ。あたしが恥ずかしいじゃん。「とりあえず出ましょう」と菜摘と村役場を引っ張って外に出る。
「きっとこの辺はどこも断られるよ。追加料金払うとか、交渉してもいいけど面倒臭くない?いっそあそこでいいんじゃない?」と提案する。ふたりは知らなさそうなのでタクシーで案内する。「狸穴坂下った辺りで」と運転手さんに言えば、どこへ行くかわかってしまうようなものだ。六本木のそこはその手の人種にご用達なホテルだから複数で入れる。受付の女性も黒服に蝶ネクタイの従業員さんも慣れている。
気に入ってる部屋は満員だった。あまり好きじゃない岩窟王の部屋に入る。ここは天井も壁も岩っぽくボコボコしてる。あたしはベッドの上に立ってお客さんを踏む際に、頭をその岩にぶつけ血を滲ませた記憶があって好きじゃないのだ。
三人でやるのはマヌケだった。この場合は菜摘が仕切るべきなのだが、あまり手順がよくなくて素人臭かった。ワンちゃん村役場は気の弱いマゾだと聞いていたが、あたしから見たらただのエゴマゾだった。アレもコレもしたいと思ってる癖に、口に出すのが恥ずかしいか面倒だかの理由でずっと無言。アレとかコレだって大したイマジネーションも感じられないのような、ごく普通な性行為なのだ。イチャイチャするのを嫌がらない女を金で求めているだけだ。リアルな奥さんとか恋人とかコミュニケーションの必要な関係では、そういうわけにはいかないのだろう。あたしたちは貰えるものが貰えれば全然構わないのだけど、男性のこうした気弱さというか傲慢さを垣間見ると世を諦めたみたいな境地になる。
ワンちゃん村役場を駅で見送ってから菜摘と少し飲みに行った。最近は青森の実家に帰ってお見合いをしたらしい。相手も東京で仕事してるひとだからこっちでも会う予定だと言ってた。気に入ったのかどうかは不明だが、まあ適当な感じなのか繋げておきたい感じだった。そうだよね、年取るからね、不安だよね、みたいな話に落ち着けて彼女とは別れ帰宅した。
家について鏡を見た。舌のキノコの成長具合を確認する。ばらばらに伸びている。眉毛を切る用の小型挟みでちょっと切ってみた。エノキタケみたいなのがぽろぽろ落ちる。ああ、あたしもどうなっちゃうんだろうなと少し沈んだ気分になる。
落ちたキノコを片付けなきゃと充電式掃除機を取りに行った。薄暗い部屋の床を掃除しようとしたとき、異様なものを見た。親指サイズの変なものが床にいる。屈んで目を凝らすと、それは人型をしている。皺くちゃの老人顔をした微細なもので白い三角帽子を被り緑色っぽい服を着てる。そいつがあたしの舌から落ちたキノコを腕いっぱいに抱えていた。
「何見てんだよ。捨てるんなら貰ってもいいだろ」とその皺くちゃな小人は高い声で喋った。
※これは完全なるフィクションです。
Android携帯からの投稿
CopyRight (C)All rights reserved by ro japan agency