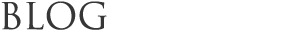-
ベルナルド・ベルトルッチの初期の3作品を観終わった。
1968年の『ベルトルッチの分身』は一番とっ散らかっていて、ワケワカリマセ~ンの世界。でも同時にかなり重要な作品であることは確か。
ベルトリッチにとって初めてのカラー作品。鮮やかな色の洪水。影響を受けた偉大な作家、作品へのオマージュ、革新的な手法の実践。若く尖った瑞々しさに溢れている。
ドストエフスキーの『二重人格』を一応、元にしてる。ロシアの政治、革命は、ベルトリッチの中で常に存在していたと思われる。
真面目な主人公の青年は大学の演劇クラスで教鞭を取っている。冒頭のカフェの場面で、耳栓を取るといきなり音声が大きくなる。つけると音声はこもる。ピアノを弾く友人を何故か殺すのだけど、ここでも耳栓効果が使われる。天井には巨大な扇風機の影が回ってる。
影効果はデンマークのカール・テオドア・ドライヤーの『吸血鬼』っぽい。建物の壁に自分の巨大な影が映り、分離するとことか。それはいつしか狂暴な分身になり、アパートで同居することになる。狙ってた女の子とのデート(駆け落ち?)では狂暴なやつが担当。
洗剤の訪問販売の女性(写真の上)を洗濯機の泡の中で殺害する場面は妙にエロい。死んでも瞼に描かれた目は開いている。
ベルトルッチの父親の友人だった詩人で映画監督のパゾリーニ(ソドムの市のひと)の影響も見られる。のちの『ラストタンゴ・イン・パリ』で爆発した才気の元が現れているように見えた。
その時代にどんどん上に行ってしまったゴダールっぽい吹き替えとか、イタリア映画のゴージャスな雰囲気(フェリーニ?って感じ)とか、いろんな要素がてんこ盛り。『戦艦ポチョムキン』みたいな階段広場では乳母車が転倒し、赤や白の発煙筒を持ったひとが左右に行き交う。エンニオ・モリコーネの大袈裟な音楽は時に爆音になって、劇場にいるかのような気分になる。
ギロチンで切った足や首が勝手に動き回る、別の存在になって息をする、演劇の死は映画の誕生、分身は自分であり別のものでもある、共存してこそがアート。そんなテーマが後半で見え隠れしたように感じた。
この作品は日本では今まで未公開だったそう。ソフト化もされていなかった。とても勿体無いことだと思う。
CopyRight (C)All rights reserved by ro japan agency