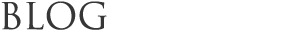トム・アット・ザ・ファーム
暴力が官能に変わるとき
『わたしはロランス』で映画ファンの心を鷲掴みにしたグザヴィエ・ドラン監督の4作目は、まさかのサイコサスペンス。彼の武器である洗練されたビジュアルセンスは封印され、凡庸なものをそのまま並べ立てたようなリアルさが新鮮だ。ミシェル=マルク・ブシャールの同名戯曲の映画化で、ワンシチュエーションだった舞台劇の面白さを残しつつ、映像ならではの効果が生かされている。ドラン自ら演じるトムがケベックの農場を訪れる場面から始まり、年老いた女性との接触、野蛮な男の登場と、無駄な説明を排除した流れに緊張が走る。亡くした恋人の生家に囚われ、暴力を受けながらも逃げ出さない、異様な精神状態の描写が絶妙だ。最愛の息子を失い悲しみに暮れる母と、いつまでも愛されない兄の関係はピリピリとして、その間を取り持つ役割も担うトム。金色に染めた髪で走るトウモロコシ畑、枯れた草に切られる肌、家畜の生々しい匂い、男同士で儀式のように踊るタンゴなど、濃密で息苦しくなるようなエロ感覚でいっぱいだ。既存のポップミュージックを多用するのがドラン作品の特徴でもあるが、今回は映画音楽作曲家、ガブリエル・ヤレドとのコラボレーションという新たな試みをしている。その重厚な音の背景により、クラシカルなサスペンス映画のような雰囲気も醸し出していた。(山田ルキ子)